岩本 康志
| ① 財政政策の有効性の評価には,通常の乗数ではなく均衡予算乗数を用いるべきだ。通常の乗数には,持続可能でない政策を前提とし,支出拡大と減税の選択に対して誤った判断を与える,という問題点がある。 ② 均衡予算乗数の最大値は「1」であり,財政支出に民間需要拡大効果はない。乗数の低下要因として指摘されている消費性向,輸入性向の変化は,減税乗数を低下させるのであって,均衡予算乗数には影響しない。 ③ 財政出動の判断で重視すべきは,経済安定化機能よりも資源配分機能である。支出の費用と便益の厳密な吟味が不可欠である。 |
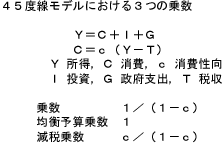 財政政策が最も功を奏する局面(経済に遊休資源が存在し,民間部門に雇用されている資源に影響を与えず,公共事業をおこなえるとした場合)での,通常の乗数,均衡予算乗数,減税乗数の計算例を表に示してある。この場合,均衡予算乗数は「1」となり,それと減税乗数の和が通常の乗数となる。
もし遊休資源が存在しなければ,政府支出はすでに民間部門で使用されていた資源を代替するだけで,所得増はまったく生じない。このとき,均衡予算乗数は「0」になる。経済の遊休資源の状況により,均衡予算乗数は「0」と「1」の間に位置することになる。
均衡予算乗数は,消費性向や(輸入が可処分所得の関数である限り)輸入性向に依存しない。乗数効果の低下の理由としてこうした変数の変化が指摘されているが,それらは減税乗数の低下を意味しているのであって,均衡予算乗数には関係ない。財政政策の有効性低下をめぐる最近の議論は,いくぶん迷路に陥っているようである。
また,均衡予算乗数の最大値が1であることは,財政支出が民間需要の拡大効果をもたないことを意味している。通常の乗数では,最初の需要増が所得から派生的に需要増が生み出されてくる。均衡予算乗数の違う点は,派生的な需要増が財政支出の財源調達によって吸収されてしまうことである。財政政策での民間需要拡大効果は同時におこなわれている減税政策によって生じているのである。
財政政策が最も功を奏する局面(経済に遊休資源が存在し,民間部門に雇用されている資源に影響を与えず,公共事業をおこなえるとした場合)での,通常の乗数,均衡予算乗数,減税乗数の計算例を表に示してある。この場合,均衡予算乗数は「1」となり,それと減税乗数の和が通常の乗数となる。
もし遊休資源が存在しなければ,政府支出はすでに民間部門で使用されていた資源を代替するだけで,所得増はまったく生じない。このとき,均衡予算乗数は「0」になる。経済の遊休資源の状況により,均衡予算乗数は「0」と「1」の間に位置することになる。
均衡予算乗数は,消費性向や(輸入が可処分所得の関数である限り)輸入性向に依存しない。乗数効果の低下の理由としてこうした変数の変化が指摘されているが,それらは減税乗数の低下を意味しているのであって,均衡予算乗数には関係ない。財政政策の有効性低下をめぐる最近の議論は,いくぶん迷路に陥っているようである。
また,均衡予算乗数の最大値が1であることは,財政支出が民間需要の拡大効果をもたないことを意味している。通常の乗数では,最初の需要増が所得から派生的に需要増が生み出されてくる。均衡予算乗数の違う点は,派生的な需要増が財政支出の財源調達によって吸収されてしまうことである。財政政策での民間需要拡大効果は同時におこなわれている減税政策によって生じているのである。